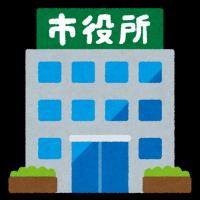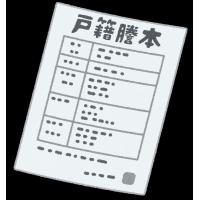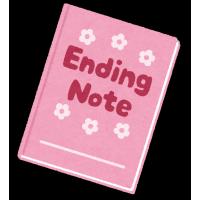医療法人の設立認可申請

現在、個人開設として診療所を運営している医師、歯科医師のみなさまへ
出資持分のある医療法人を新たに設立できなくなってから10年以上が経過。
それ以来、医療法人は基金制度という仕組みが採用され、それまで社員による出資によりその財産を確保していた構造から、医療法人が診療所を運営するのに必要な財産は基金拠出することとなりました。
そして、ある一定の条件が満たされた時に、基金拠出した者にその返還義務を負うものとなりました。これには利息を付すことはできないので、当倍返しとなります。
出資持分に応じた払い戻しという概念が無くなったことで、どれほど医療法人が売り上げを計上して成長しても剰余金の配分という経済的利益は消滅しましたが、その分、相続対策が不要となったことも事実です。
それでは、経済的恩恵が無くなったので、医療法人化を目指すのは無意味なのか?
答えはノーです。
これまで通り、税制面においては、個人所得オンリーから法人税と給与所得に移行できる分の節税メリットは健在。
また、退職金の準備等も行うことができ将来設計が立てやすくなります。
一方、手続き的側面で言うと、個人診療所の場合は、その個人(管理者)の死亡により診療所は廃止となりますが、法人運営の場合は、診療所の管理者個人が死亡したことだけでは診療所の廃止と直結しません(単なる管理者の変更手続きをすれば良い)。
その他、管理者を必ず理事に加えないといけないという制約があるものの、医療法人ならば診療所をいくつでも開設することが可能となります(同じのれんを全国に展開することも可能になります)。
ただし、もちろんデメリットもあります。
個人診療所の場合は、保健所が所管で、保険診療を行う場合の関東信越厚生局での手続きを入れても、この2箇所が管轄行政のメインとなりますが、医療法人の所管は都道府県となりますので、医療法で定められた定期的な届け出等が必要となったり、これまでの管轄行政が1つ増え、3箇所となり、行政手続きが煩雑化することになります。
また、社会保険の強制加入等も経営者の負担増となります。
これらを総合勘案して医療法人化を検討する必要があります。
商品サービス情報一覧
企業情報
- 企業名
- 柴崎行政書士事務所(事業所概要詳細)
- 所在地
-
東京都新宿区